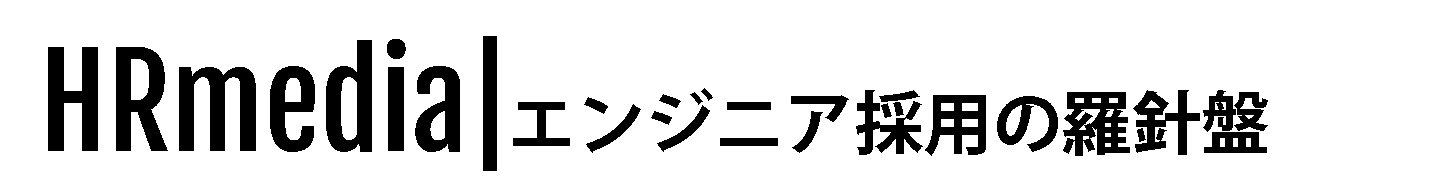みなさん、こんにちは。みなさんはイスラエルについてどのようなイメージを持っていますか?
文化的にも政治的にも様々な観点から話題となるイスラエルですが、スタートアップ大国、IT大国としても知られています。
イスラエルは、国民一人当たりのVC投資額、NASDAQ上場企業数、年間のスタートアップ数といった指標では軒並み世界トップを維持しており、GoogleやIBM、Facebookといった名だたるテックジャイアントが研究開発拠点を置くことからもIT業界におけるその存在感の大きさが伺えます。現在日本には約500名のイスラエル人が働いており、彼らの活躍が日本のIT業界を陰ながらに支えているのです。
そこで今回はイスラエル出身のエンジニア・レビー・ドロールさんに日本のIT業界について、様々な角度からお聞きしました。
近年、日本のIT業界は世界的な影響力を失っていると言われていますが、イスラエル出身のベテランエンジニアの言葉には、今後の日本のIT業界を活気づけるインサイトが隠されているかもしれません。

イスラエル生まれ。15歳からソフトウェアエンジニアとして活動。2017年に来日。ベンチャーを経て、大手ホテルチェーンにてエンジニアリングマネージャーとして勤務。
スタートアップ大国イスラエルから世界へ
–はじめにドロールさんの経歴を教えてください
イスラエルで生まれ育った私は、高校性の時からソフトウェアエンジニアとして働いていました。はじめは、クリニック向けのシステム開発の受託から始まり、その後、証券会社や銀行向けのシステム開発に従事しました。2008年のリーマンショックで大規模なレイオフがあったことで、金融業界を後にすることになったのですが、当時の同僚に、スタートアップの立ち上げに誘われて、開発者として参画することとなります。
私たちは、まず初めに、架空のデジタル通貨によるトレードでユーザー同士が競い合うというゲームを開発したのですが、そのプロジェクト自体は、あまり成長はしませんでした(笑)。
スタートアップなので、その後、何度も軌道修正をしながら様々なプロジェクトに着手していったのですが、会社に転機が訪れたのは、バイナリーオプションのシステム開発を始めたことでした。
私たちは、バイナリーオプションのシステムの開発を通じて、各国の金融機関とパートナーシップを結んでいくことで成長していき、最終的には業界で世界3位の規模まで成長しました。日本の大手金融機関ともパートナーシップを結んだ事もありますね。私もチーフソフトウェアアーキテクツとなり、エンジニアの数も100人を超えるまでに成長し、ビジネスの幅を広げていきました。
私たちは、EUを主要なマーケットとして見据えていたため、開発拠点をブルガリアに置いていたのですが、私は、創業から9年程してから、その会社を退職することになります。
ある程度の成功をおさめることができて、一区切りがついたのと、ブルガリアでの生活にあまり満足できなかったためです。ブルガリアは、マーケットが小さく、産業も限られており、出来ることには限界がありました。
–日本に来たキッカケを教えてください

元々、日本が好きだった私は、それまでに公私を問わず、何度も日本に来てたのですが、あらゆる設備が整っており、医療費も安く、住みやすい国だと興味を持っていました
後に日本に拠点を移すことに決めた私は、何人かの友人にデカルトサーチ代表のパスカルを紹介してもらい、日本での就職活動を開始しました。ベンチャー企業での勤務を経て、現在は、ホテルやレストランチェーンを運営する企業で、エンジニアリングマネージャーとして働いています。
イスラエル人エンジニアの見た日本のIT業界
–日本のIT業界についてどう思いますか?
シリコンバレーほどではないかもしれませんが、日本には健全で多くの雇用を創出するIT産業があります。
これは、スタートアップやベンチャー企業にとって非常に良い環境と言えます。国内で開発者やIT人材を賄えるという環境は、世界を見渡してみると、当たり前のことではありません。私たちは、幸いにもブルガリアで優秀な開発者を見つけることが出来ましたが、一般的には、優秀なエンジニアを海外からブルガリアに招致するのは大変なことです。
日本のIT産業には課題もありますし、より良い環境の国は、いくつかはあるかもしれませんが、世界的に見ると、とても健全なマーケットがあると思います。
–近年、世界で活躍できる日本のITスタートアップはほとんどなく、その閉鎖性が指摘されますが、どうお考えですか?

スタートアップ業界に限ったことではありませんが、日本は、クローズドなマーケットだと思います。しかし、それは悪いことばかりではなく、メリットもあります。
日本のマーケットに特化したサービスを開発しても、海外展開する際には、それが全く役に立たないということは珍しくありません。そのため、日本で成功するためには日本に特化したサービスを開発しないといけないと言われていますね。しかし、そのような閉鎖性は、実は日本の企業にとってチャンスであるとも言えます。
振り返ってみると、GAFAのようなグローバル企業でさえも、日本のマーケットに進出して、十分に普及するのには長い年月を要しました。この時間的猶予は、同じ業界でサービスを展開する日本企業にとって成長するチャンスを与えてくれるのです。
例えばRubyは日本で生まれ、日本のマーケットで受け入れられてから、他の国に徐々に広がっていきましたね。
仮に、日本人がアメリカでスタートアップを始めるとすると、その日から過酷の競争の下にさらされます。膨大な予算を持つシリコンバレーの競合にコピーされることなんて日常茶飯事ですし、次の日にはGAFAのようなテックジャイアントが参入してくるかも知れません。
もちろん、日本で成長した後に、海外展開で成功できるかどうかは別問題ですが、考えてみてください。もし、日本が他のほとんどの国と同じように、国内のマーケットが小さく、参入障壁もなく、多くの産業で多国籍企業がすでにシェアを握っているとしたら、もう国内のスタートアップに成長のチャンスは残されていません。
中国も国内のマーケットをクローズドなものにするために様々な努力をしていますが、それには相応のメリットがあるからやっているのです。中国は、外資規制などの保護規制が強く、外国企業が気軽に会社を設立する環境ではなく、GoogleもFacebookもありません。中外合弁企業を作るにしても様々な規制があります。
例えば、中国発のTikTokは現在、世界展開をしていますが、初期の段階では、海外の競合が参入しづらい中国のマーケットで成長してから、海外のマーケットでレバレッジをかけるという手法で展開していきました。
ただ、日本の国内マーケットは、ある程度の大きさがあるので、日本の企業は国内のマーケットで満足し、海外展開に消極的になることもあります。日本人の全員がそうだとは言うつもりは決してありませんが、大企業を中心として、そのようなコンサバティブな傾向を感じることはあります。
しかし、現状維持で満足するのかどうかは、メンタルの問題です。野心的になればチャンスがありますし、最近は、日本でも海外展開に対して野心的なベンチャー企業は増えてきていると思います。
-日本で働いてみてエンジニアの待遇や労働環境についてどうお考えですか?

まず、待遇についてですが、日本におけるエンジニアの給料はリーズナブルだと思います。シリコンバレーほど高くはありませんが、他のほとんどの地域よりも高い水準です。給料だけでなく、リモートワーク、フレックスタイム、有給休暇などの側面からも魅力的なオファーを提示する企業も増えてきてますね。
労働環境については、あらゆる企業を見てきたわけではありませんが、私の見てきたなかでは、正直、あまり労働環境の良くない会社もありました。
具体的には、不必要なミーティング、必要以上に長い会議、そして、フレックスタイムの欠如などが挙げられます。また、時折、価値を生み出して会社の売上に貢献することに注力せずに、働いているように見せるために腐心するという悪い習慣も時として見受けられます。オフィスに20時間いたとしても、価値を生み出していなかったら意味がありません。
もちろん、すべての企業がそうだとは思いませんし、グローバル企業の良いところを取り入れたりしながら活躍するベンチャー企業も数多くあります。
また、日本には、非常に強い雇用保護の規制があります。アメリカやイスラエルでは、企業はいつでも従業員を解雇できることと比較すると大きな違いです。
これにはメリットとデメリットの両方があります。多くの研究で明らかになっていることですが、人間は不安を抱えているとパフォーマンスが下がります。いつ解雇されるか分からないと言う不安を抱えたまま仕事をするのは健康的ではありません。
そのような不安がなく働ける環境があることは心理的には良いことです。終身雇用があるからこそ、人々は住宅ローンを組むなどといった長期的なプランが立てられます。
ただ、雇用が保証されすぎていても労働意欲がなくなります。そのため、近年、多くの企業では契約社員と正社員のバランスを取ることでこの問題も解決しようとしていますが、これは極めて現実的な解決策のように思えます。
日本の労働環境に関しては、良い面と悪い面がありますが、最近は、旧態依然とした会社も改革しようと努力しているように見えます。
重要なのは、日本における労働環境の改革は、法律が変わったから起こったのではなく、企業や個人による、自発的な意識の変化によりもたらされたということです。
イスラエルがスタートアップ大国となった理由
–一方で、イスラエルはスタートアップ大国と言われていますが、それには、どのような要因があると考えていますか?

これには様々な要因が挙げられます。まず大きな要因として、私は、兵役の存在が影響していると考えています。イスラエルでは、国民全員が兵役の義務があります。
イスラエル軍には、大規模なテクノロジーセクターがあり、そこでは、プログラミングやネットワーク管理、組織のマネージメントといったことも学ぶのですが、軍の指揮官に求められる能力、すなわち、5、6人の小隊をマネージメントする能力は、スタートアップのチームを構築してマネージメントする能力と多くの共通点があるのです。
言うまでもなくスタートアップにとって初期メンバーのチームアップは、最も重要だと言えますが、イスラエルでは兵役時代に、緊密で強いネットワークができるので、創業時に非常に役にたちます。実際に、兵役時代の友人とスタートアップを始めるケースは非常に多いです。
また、一般化しすぎるのは良くないですし、全員がそうではありませんが、イスラエルでは、大企業に就職するよりも、スタートアップを始めて、自分の会社を持つことを目標とする若者が多いですね。
これには様々な理由があるでしょうが、個人的には建国の背景が関係していると考えています。ご存知のようにイスラエルは、建国70年そこそこの若い国です。建国当時は、何の産業もなく、砂漠しかなかったため、すべてゼロから作らなければなりませんでした。
当時の人々は、自分達の力でゼロから国を強く、豊かにしていくというビジョンを持っていたため、そのような環境が「何かをゼロから作るというスタートアップ精神」を育んできたのかも知れません。
ただ、このようなマインドセットも今後も永久に続くのかは分かりません。世代によっても考え方は違いますし、周囲を敵国に囲まれ、貧しく脆弱だった50年前に比べたら、国防力も十分に備わり、ずっと豊かになっているので。あと数十年たてば、人々の考え方も変わっているかもしれません。
日本のIT業界は何を目指すべきか
–日本でプログラミング教育が開始されましたが、どのようなものであるべきだと考えていますか?

日本のプログラミング教育の教育要綱の詳細は見ていませんが、どのように教えるのかは非常に重要です。
重要なのはコンピューターサイエンスとエンジニアリングをバランスよく教えるということです。
学校教育においては、プログラミングそのものに加えて、数学やコンピューターサイエンスの基礎を学ぶことは非常に重要です。実際の現場におけるエンジニアの業務と言えば、ライブラリを参照してコードを組み合わせるといった業務が大部分であり、アルゴリズムを設計したりする機会はほとんどありませんが、コンピューターサイエンスの知識や理論を理解していることで、組み合わせの幅が広がります。
ただ、高校や大学でコンピューターサイエンスを専攻していても、SQLについて何も知らないといった新卒エンジニアにデータベース管理は任せられません。学校でコンピューターサイエンスの側面とエンジニアリングの側面は、両方バランスよく教えることが重要だと思います。また、ITのトレンドは移り変わりが激しいのでトレンドを見据えるのも重要です、未来永劫に残る技術などありませんから。
–これからはIT業界ではどのような人材が活躍できると考えていますか?

よく言われることではありますが、いわゆる、T型人材を目指すべきであると考えています。T型人材とは、ひとつの分野に深く精通しつつも、他分野に関しても幅広い知識を持つ人材のことを指します。IT業界では、このような人材は幅広く活躍できると考えています。
React.jsでもSQLでも分散システムでも何でもよいので、何か専門分野をひとつ作りましょう。それを徹底的に追及すると同時に、専門外の知識も幅広く吸収する、そんな人材はどんな企業でも活躍できます。
専門分野じゃないから出来ませんといった姿勢ではなく、専門分野じゃないけど時間をくれたらキャッチアップ出来るといった姿勢の方が、チーム内でも評価に繋がります。特に小さな会社ですと、非専門分野の業務も手伝ったりする必要がでてくるわけですから。